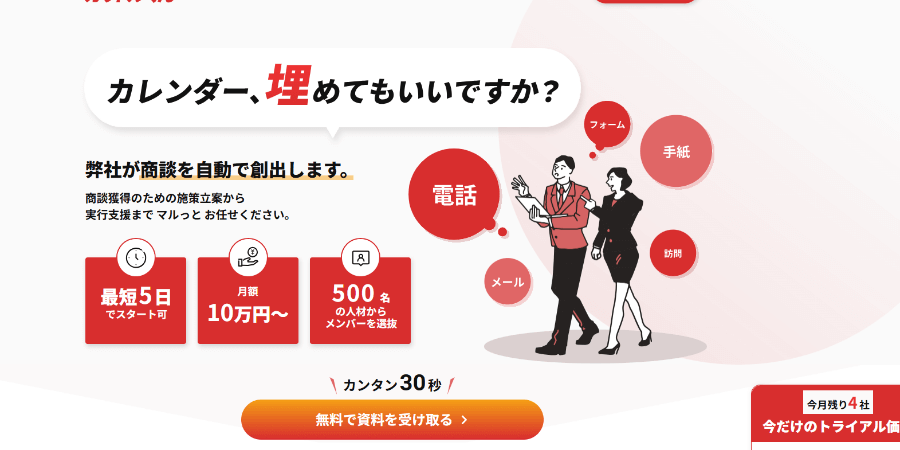営業代行とは?向いている企業や選び方、「やめとけ」と言われる理由も解説
- カリトルくん 【営業代行サービス】
- 記事制作日2025年10月30日
- 更新日2026年1月6日
- 0いいね!
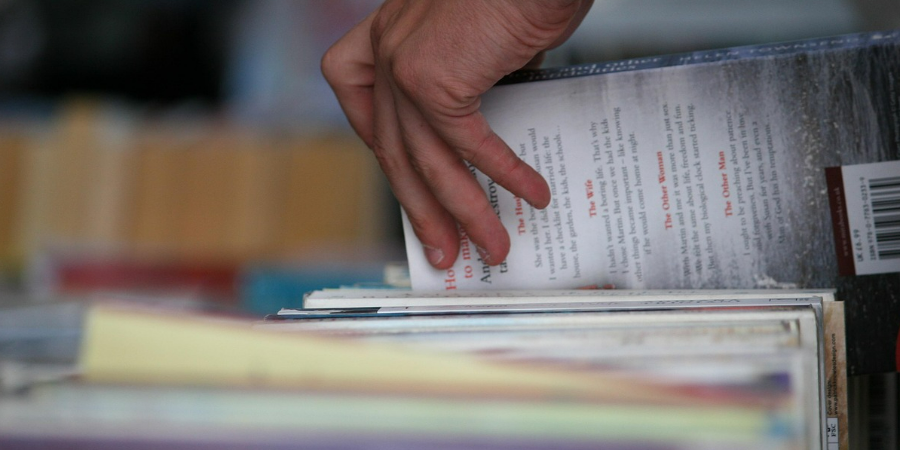
営業活動を強化したいけれど、社内に人材もノウハウも足りない。
そんな悩みを抱える企業が増えています。採用コストの上昇や人手不足のなかで、効率的に成果を出すにはどうすればよいのでしょうか。そこで注目されているのが「営業代行」です。
営業代行を活用すれば、経験豊富な営業のプロが代わりにアプローチや商談を行い、最小のリソースで最大の成果を狙うことが可能です。本記事では、営業代行の種類や料金体系、失敗しない選び方、向いている企業・向かない企業の特徴、そして活用メリットまでを徹底解説します。営業代行を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
営業代行とは
営業代行とは、企業の代わりに営業活動を行う外部サービスのことです。新規開拓や商談獲得、既存顧客のフォローなど、営業プロセスの一部または全体を委託できるのが特徴です。主な種類としては以下の4つに分けられます。
- テレアポ代行
- インサイドセールス代行
- フィールドセールス代行
- カスタマーサクセス代行
それぞれの特徴や活用シーンを理解することで、自社に最適な営業代行の形を選ぶことができます。以下では、各営業代行の内容を詳しく解説します。
テレアポ代行
テレアポ代行は、電話で見込み顧客にアプローチし、アポイントを獲得するサービスです。リストに基づき営業担当者が架電を行い、商談につながる見込み顧客を選定します。自社で営業リソースを確保できない企業や、短期間で多くのリードを獲得したい場合に有効です。
成果報酬型が多く、1件あたりのアポ単価は1万〜3万円程度が相場です。スクリプト作成やトーク改善を代行業者が担うため、効率的なアプローチが可能になります。
インサイドセールス代行
インサイドセールス代行は、オンラインや電話を用いて商談前のリードを育成するサービスです。マーケティングで獲得した見込み顧客に対し、課題のヒアリングや提案を行い、商談化率の高い顧客を営業部門へ引き渡します。
SaaSやBtoBサービスで導入が進んでおり、顧客データを活用した継続的な接触が特徴です。リードナーチャリングによって、営業効率を大幅に高めることができます。
フィールドセールス代行
フィールドセールス代行は、実際に顧客先へ訪問して商談や契約締結を行う代行サービスです。高単価商材やBtoB取引など、対面での提案力が求められるケースに適しています。提案資料の作成やプレゼンも代行可能で、営業経験豊富な人材が担当することが多いです。
近年ではオンライン商談の普及により、訪問とWeb提案を組み合わせたハイブリッド型も増えています。
カスタマーサクセス代行
カスタマーサクセス代行は、契約後の顧客フォローを専門に行うサービスです。利用状況の分析や定期的なコミュニケーションを通じて、顧客満足度を高め、解約を防止します。
特にサブスクリプション型サービスやSaaS企業で需要が高く、顧客との関係構築を重視する点が特徴です。サポート体制を整えることで、LTV(顧客生涯価値)の最大化にもつながります。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
営業代行会社の料金体系と費用相場
営業代行会社の料金体系は、成果報酬型・固定報酬型・複合型の3つに大きく分けられます。依頼内容や目的に応じて、どの形式が最適かを見極めることが重要です。料金相場を理解しておくことで、費用対効果を正しく判断でき、無駄なコストを防ぐことができます。
以下では、それぞれの特徴と費用感について詳しく解説します。
成果報酬型
成果報酬型は、アポイント獲得や契約成立といった成果に応じて費用が発生する仕組みです。初期費用を抑えやすく、結果に対して支払うため、リスクを抑えたい企業に適しています。
テレアポ代行では、1件あたり1万〜3万円前後の報酬が一般的で、業界や商材単価によって変動します。成果が出ない限り費用が発生しない一方で、アポの質が担保されにくい点や、商談数を稼ぐことを優先する業者もあるため、成果基準の明確化が重要です。
固定報酬型
固定報酬型は、月額制で一定の費用を支払い、決められた範囲内で営業活動を行うプランです。平均的な料金相場は月10万〜60万円ほどで、活動内容(架電数・商談数・レポート頻度など)によって異なります。
成果に関係なく費用が発生しますが、安定的な稼働を確保でき、長期的な戦略に基づく改善が進めやすい点がメリットです。特に、リード育成やデータ分析を重視する企業に向いています。
複合型
複合型は、固定報酬と成果報酬を組み合わせた料金体系で、近年最も多く採用されています。基本料金で最低限の稼働を保証しつつ、アポ獲得数や成約数に応じて追加報酬を支払う形です。例えば、月30万円+成果1件あたり2万円といった形式が一般的です。
営業代行会社の失敗しない選び方
営業代行会社を選ぶ際には、「業種実績」「営業手法」「予算適性」の3点を確認することが重要です。これらを見落とすと、成果が出ないだけでなく、無駄なコストが発生するリスクがあります。自社の目的と営業代行会社の強みを正しくマッチングさせることで、長期的な成果につながるパートナーシップを築けます。
以下で、それぞれのポイントを解説します。
自社と同じ業種で実績があるか確認する
営業代行会社を選ぶうえで最も重要なのは、自社と同じ業界・商材での成功実績があるかを確認することです。業界特有の商談構造や意思決定プロセスを理解していないと、成約率が大きく下がります。
たとえば、IT業界では課題ヒアリング型の提案が求められる一方で、建設業では信頼関係の構築が重視されます。実績は公式サイトや事例ページで確認できるほか、可能であれば担当者に過去のKPI改善データを提示してもらうとよいでしょう。
営業手法は幅広いか確認する
営業代行会社によって、得意とする手法(テレアポ、オンライン商談、展示会リード対応など)は異なります。複数の営業手法を組み合わせられる会社を選ぶことで、顧客の購買段階に応じた柔軟なアプローチが可能になります。
たとえば、BtoB企業ではインサイドセールスでのリード育成後にフィールドセールスを行う二段構成が効果的です。営業プロセスのどこを代行するのかを明確にし、複数チャネルで成果を出しているかを確認しましょう。
予算にマッチしているか確認する
営業代行サービスはプラン内容や成果報酬の基準によって大きく費用が異なります。自社の予算に対して、どの程度の成果を期待できるかを事前にシミュレーションすることが重要です。
短期的なアポ獲得だけを狙う場合と、長期的なリード育成を目的とする場合では、必要なコスト構造がまったく異なります。また、見積もりの段階で「成果定義」と「レポート範囲」を明確にしておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
営業代行会社がおすすめな企業の特徴
営業代行会社の活用が特に効果的なのは、営業リソース不足・ノウハウ不足・高単価商材を扱う企業です。これらの企業では、自社で営業体制を整えるよりも、外部の専門家に委託することで成果を出しやすくなります。
以下では、それぞれの特徴と営業代行が有効に機能する理由を詳しく解説します。
自社に営業のリソースがない
営業代行は、人手や時間が足りない企業にとって最も効果を発揮する選択肢です。特にスタートアップや少人数の中小企業では、経営者や他部署の社員が営業を兼任しているケースも多く、リード獲得や追客まで手が回らないことがあります。
営業代行を活用すれば、架電やアプローチ、商談調整などを一括で任せられ、経営資源を本業に集中させることができます。短期的な成果を求めるフェーズでも有効です。
営業のノウハウがなく、適切な施策がわからない
営業経験が乏しい企業では、どのようにターゲットを設定し、どの段階でアプローチするかといった戦略設計のノウハウが不足していることが多いです。営業代行会社は、リード管理やスクリプト作成、商談化率向上など、体系的な手法を持っています。
そのため、単なる代行ではなく「営業設計の外部パートナー」として機能します。ノウハウを共有してもらうことで、将来的に自社内で営業体制を構築する基盤づくりにもつながります。
サービス単価が高い
高単価商材(例:BtoBSaaS、不動産、コンサルティングなど)を扱う企業では、1件の成約で大きな売上を得られるため、営業代行との相性が良いです。アポ単価や契約単価が高くても、LTV(顧客生涯価値)で見れば十分なリターンが見込めます。
経験豊富な営業代行チームが商談を行うことで、クロージング率を高められ、リードの質を精査する仕組みも整います。コストよりも成果を優先するビジネスモデルに向いています。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
営業代行会社がおすすめできない企業の特徴
営業代行は多くの企業で有効ですが、業界特性や商材の性質によっては成果が出にくいケースもあります。特に「専門性の高いサービス」「機密性の強い業務」「低単価ビジネス」では、自社で営業を担うほうが効果的です。
ここでは、営業代行を導入すべきでない代表的な3つの特徴を解説します。
サービスに高度な専門知識が必要になる
法律、医療、IT開発などのように、高度な専門知識や資格が必要な商材を扱う場合、営業代行との相性はよくありません。外部の営業担当者が製品やサービスの本質を理解しきれず、誤った説明をするリスクがあるためです。
特に専門用語や技術的な要素が多いBtoB領域では、営業担当者の理解度が成果に直結します。こうした業種では、社内で専門知識を持つ担当者を育成し、顧客との信頼関係を築く体制が求められます。
機密情報を扱うことが多いサービスである
顧客情報や財務データなど、高い機密性を持つ情報を取り扱う企業では、営業代行の利用は慎重に検討する必要があります。外部委託により情報漏えいのリスクが生じるだけでなく、セキュリティポリシーの遵守徹底も難しくなります。
たとえば、士業や人材紹介業などでは、顧客データの取り扱いが厳格に管理されており、契約前の段階で外部アクセスが制限されることもあります。社内に専任の営業担当を配置し、リスク管理を優先する方が安全です。
サービス単価が低い
営業代行の費用は一定水準を超えるため、低単価商材では採算が取りにくくなる点に注意が必要です。たとえば、単価1万円未満の商品を販売するケースでは、アポ獲得単価や営業コストが利益を圧迫します。
成果報酬型であっても、アポ単価が数万円に達することが多いため、継続的なROI確保が難しいでしょう。低単価ビジネスでは、広告運用やECサイトなど、オンラインチャネルによる自動化施策のほうが費用対効果が高くなります。
「営業代行業者はやめとけ」と言われる理由
営業代行には多くのメリットがある一方で、「やめとけ」と言われるのは主に費用対効果や透明性の問題が原因です。特に、契約内容や成果の定義を曖昧にしたまま依頼すると、期待した結果が得られないリスクがあります。
ここでは、営業代行に対してネガティブな印象を持たれやすい4つの理由を詳しく解説します。
コストが高く費用対効果が合わない場合がある
営業代行の中には、初期費用や固定報酬が高額に設定されているケースがあります。成果が出るまでに時間がかかる場合、投資に見合ったリターンを得られないこともあります。また、安価な業者を選ぶと、対応品質が低く、逆にブランドイメージを損ねるリスクも存在します。
契約前に「成果が出るまでの期間」と「想定CPA(顧客獲得単価)」を算出し、費用対効果をシミュレーションしておくことが重要です。
自社にノウハウが蓄積されない
営業代行に依存しすぎると、自社に営業ノウハウが残らないまま契約が終了してしまうという問題があります。営業戦略や顧客データが外部に偏ることで、社内の再現性が低下し、次回以降の施策に活かせません。
特にスタートアップや新規事業では、自社で学習・改善する仕組みが欠かせません。営業代行を利用する場合は、レポート共有や定期ミーティングなど、知見を社内に取り込む体制を整えることが大切です。
営業活動が可視化されにくい
営業代行の課題として多いのが、営業プロセスがブラックボックス化しやすいことです。架電数や接触内容、失注理由などが明確に共有されないと、改善の打ち手を検討できません。
これを防ぐためには、KPI(アポ率・商談化率・成約率)を可視化するレポートを定期的に受け取れるか確認することが重要です。CRMツールや共有スプレッドシートを使って、進捗をリアルタイムで把握できる体制を整えましょう。
サービスによってアポ率が変わる
営業代行の成果は、業界・商材・ターゲット層によって大きく変動します。例えば、法人向けのSaaS商材ではアポ率10%前後が平均ですが、BtoCサービスでは1〜3%にとどまるケースもあります。
つまり、他社の成功事例をそのまま自社に当てはめるのは危険です。商材特性を理解し、成果指標(KPI)を現実的な水準で設定することが、失敗を避けるポイントです。
営業代行を依頼するメリット
営業代行を導入することで、人件費削減・即戦力の確保・柔軟なコスト管理といった経営上の利点を得られます。特に、採用難や人手不足に悩む中小企業にとって、外部の専門チームを活用することは、スピードと成果を両立する有効な手段です。
以下では、営業代行の主な3つのメリットを紹介します。
営業人材の採用・育成にかかるコストを削減できる
営業人材を採用・教育するには、人件費・研修費・時間コストが発生します。一般的に1人の営業担当を戦力化するまでには数ヶ月を要しますが、営業代行を利用すれば、即日稼働が可能です。
特に短期プロジェクトや新規事業の立ち上げ期では、採用よりもコスト効率が高く、スピーディに成果を出せます。また、離職リスクがない点も大きなメリットで、固定的な人件費を変動費に置き換えられます。
経験豊富な営業プロを即戦力として活用できる
営業代行会社には、豊富な営業経験と業界知識を持つプロ人材が多数在籍しています。彼らはスクリプト改善やターゲティング精度の向上、リード育成などを通じて、営業成果を短期間で最大化します。
自社の営業課題を分析し、最適な戦略を立てる「外部の右腕」として機能することも可能です。特に、商談化率の向上や顧客対応の質を高めたい企業にとっては、即効性のある施策として有効です。
人件費を固定費ではなく変動費として柔軟に計上できる
営業代行を活用することで、人件費を固定費から変動費に切り替えることができます。成果報酬型の契約を採用すれば、成果が出た分だけ費用を支払う形になるため、無駄な支出を抑制できます。
景気や案件数に応じて契約規模を調整できる柔軟性も大きな強みです。繁忙期のみ外注し、閑散期は縮小するなど、経営状況に合わせたコストコントロールが可能になります。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
営業代行はどこまでやってくれるの?
営業代行会社が担う範囲は、リード獲得から商談、クロージング、アフターフォローまでと広範です。ただし、どの段階を代行できるかは会社によって異なります。一般的には「新規開拓型」と「包括支援型」に分かれ、前者はアポ獲得まで、後者は契約・顧客フォローまでを代行します。
最近では、営業プロセスの可視化やCRM連携を前提としたデータドリブン型営業代行も増えています。これにより、架電数・商談化率・成約率などをリアルタイムで把握し、自社の営業改善にもつなげることが可能です。契約時には、対応範囲・報告頻度・成果指標を明確にしておくことが成功のポイントです。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
中小企業はBPOをうまく活用する時代
近年、中小企業では人材不足や採用コストの高騰により、営業・経理・人事などの業務を外部委託(BPO)する動きが加速しています。BPO(BusinessProcessOutsourcing)とは、業務の一部を専門企業に任せる仕組みであり、営業代行もその代表例です。
BPOを活用する最大の利点は、専門性を持つ外部人材を柔軟に使えることです。自社で新たに採用・教育を行うよりも低コストかつ短期間で成果を出せるため、リソースをコア業務に集中できます。特に、地域企業や中小事業者にとっては、マーケティングや営業を外注することで経営の持続性を高めることが可能です。
また、BPOを通じて業務データが蓄積されることで、経営判断のスピードや精度も向上します。社内の属人化を防ぎ、外部ノウハウを取り入れながら成長基盤を整えることが、今の中小企業に求められる経営戦略といえるでしょう。
まとめ
営業代行は、人手不足やノウハウ不足を抱える企業にとって、即戦力を確保できる有効な手段です。テレアポから商談、アフターフォローまで幅広い範囲を委託できるため、限られたリソースでも成果を最大化できます。一方で、業者選びを誤ると費用対効果が合わず、ノウハウが社内に残らないリスクもあるため注意が必要です。
重要なのは、「何を目的に営業代行を活用するのか」を明確にし、自社と同業の実績がある信頼性の高い会社を選ぶことです。さらに、KPIを共有し、定期的なレポートで進捗を可視化することで、パートナーとしての連携を強化できます。
営業代行は単なる外注ではなく、企業の成長を支える戦略的な投資です。自社のフェーズや課題に合わせて最適なプランを選び、営業力の強化と持続的な収益拡大につなげていきましょう。
また、今すぐおすすめの営業代行会社が知りたい方はカリトルくんがおすすめです。
以下より無料でご相談いただけますので、どれくらい売上が上がりそうか、どれほど再現性があるのかをぜひご確認ください
\商談を自動で創出します/
- この記事にいいね!する
この記事を書いた人
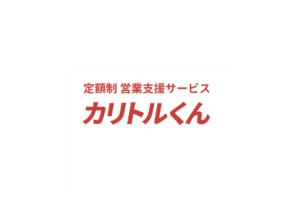
- 2いいね!
稼働ステータス
◎現在対応可能
- カリトルくん 【営業代行サービス】
職種
セールス
営業
希望時給単価
5,000円~10,000円
月額10万円から電話営業・問い合わせフォーム営業・メール営業まで、幅広い業務を依頼できる定額制の営業支援サービスです。 商談獲得の施策支援から実行支援までマルっとお任せください。
スキル
・・・登録スキルなし
スキル
・・・登録スキルなし