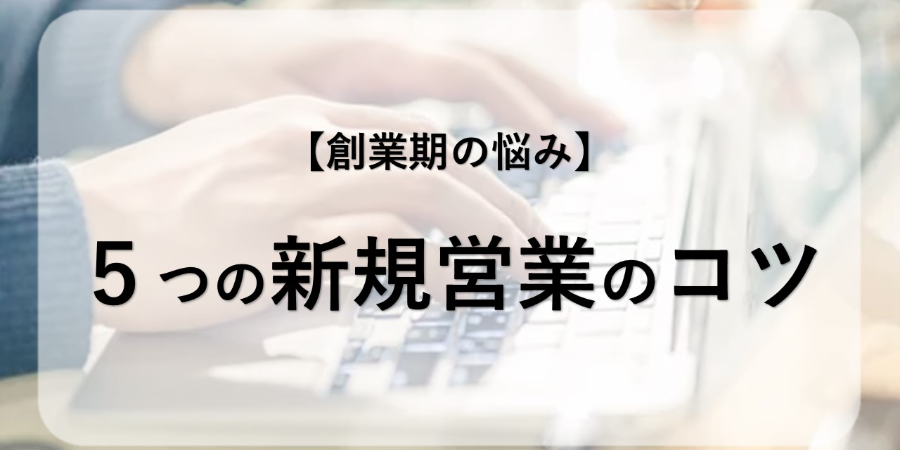Shopifyのメモの流出から学ぶAI時代の企業戦略
- Taishin Murase
- 記事制作日2025年4月12日
- 更新日2026年1月6日
- 2いいね!

「AIを使いこなせない人は、これからのビジネスで生き残れない」——そんな警句めいたフレーズを耳にすることが増えてきました。実際に、海外のEC大手のShopifyのCEOは「Shopifyでは、AIを自律的に活用する姿勢がもはや“当たり前”になっている」と明言していることが流出したメモからわかり、大きな話題を呼んでいます。今回はその流出したメモから「AI時代に企業がどう進化するべきか」を考察してみます。
Shopifyのメモに見る「AIを当たり前に使う」時代
ShopifyのCEOメモでは、冒頭から「AIの活用は社内の新しい必須スキルだ」と強いメッセージが打ち出されています。かつては専門家だけが扱うものだったAIが、いまや全社員が“当たり前に使う”ものへと変わったというのです。
特に興味深いのが、それを“推奨”や“推進”ではなく、「これからの仕事の当たり前」として位置づけた点でしょう。部署や職種を問わず、プログラミングからマーケティング、企画、カスタマーサポートにいたるまで、全員がAIを日常業務に組み込み、成果を上げることを期待されている。これは、将来に向けた“人材育成”というよりも、もはや“明日からの行動指針”だといえます。
この方針は、単なる経営トップの号令ではなく、組織全体の評価制度やリソース配分にまで及びます。AIを活用するスキルがあるかどうかが、人事評価やプロジェクトの進め方を大きく左右するようになっているのです。
ShopifyのAIに関する6つの方針
以下は、Shopifyの社内メモに書かれている「6つの方針」をベースに、それぞれの内容とそこから読み取れる考察をまとめます。前述の「AIを当たり前に使う」時代の背景に加え、具体的にどのような社内方針を掲げているのかを見ていきましょう。
1. AI活用は全社員にとって「基本スキル」である
Shopifyでは、AIを使うことが特別な能力ではなく「標準的な期待値」だと明言されています。もはや「AIが使えたらすごい」ではなく、「AIを使えないと困る」レベルに来ているわけです。これは、エンジニアやデータサイエンティストなどの専門職に限らず、マーケティング担当者からカスタマーサポートまで、職種を問わずに当てはまります。
2. 「GSD(Get Shit Done)のプロトタイプ段階」でのAI活用
GSDはShopifyの企業文化を象徴する「素早く試して形にする」アクション指針です。メモでは、プロトタイプを作る段階からAIを使いこなすことが強調されています。従来はアイデアを形にするまでに多くのリソースや時間が必要でしたが、AIによって設計・開発・ドキュメント作成などの初期作業を劇的に効率化できるからです。
これは個人的にもどの企業でも非常に使える方針だと思います。例えば、最近では簡単なLP、Webアプリ、生成AIを活用したアプリが自然言語だけで簡単に生成できます。現時点で、いきなり本番では使えるレベルは難しいですが、チームメンバーと自分の頭の中にあるアイディアを共有したり、クライアント様に提案できるレベルの物は爆速で作れます。言葉で説明するよりも、「実際に動く物」を提示することで議論の質も変わってくると思います。
3. AI活用を評価制度に組み込む
メモでは、「AIを使っているかどうか」をパフォーマンスやピアレビューで評価すると明言されています。使いこなし方や成果を出した度合いが、人事評価の材料にもなるのです。
これは社員の動機付けにおいて極めて大きなインパクトがあります。通常、新しいツールの学習には一定の時間とコストがかかるため、組織としてサポートしなければ浸透しにくい側面がありますが、評価制度で明確に位置づけられることで、習熟が加速するわけです。
4. 学習は自学が前提、しかし「共有」が鍵
Shopifyでは、自分で積極的にAIツールを使い込む姿勢がまず必須とされます。しかし同時に、「学んだことは積極的に共有し合う」風土づくりにも注力しているのが特徴です。Slackの社内チャンネルでは、プロンプトの工夫や、新機能の試行錯誤の結果などがこまめにシェアされています。
AIはツールによって使い方やバージョンアップがめまぐるしく進化します。一人ひとりが自学で最新情報を追うだけでは効率が悪い。そこで、組織内で成功事例や失敗事例を素早く回覧して「チーム全体の学習曲線」を高めることが、競争優位につながります。
5. リソース増員前に「AIでできないか」を問い直す
メモには、新しい人材や追加の投資を求める前に「本当にAIで代替できないか」を検討すべしという方針が明言されています。これは単なるコスト削減だけではなく、AIを最大限活用することで「小さなチームでも、より大きな成果を狙う」考え方を根付かせる狙いがあります。
企業の成長フェーズでは往々にして「人を増やせばできることが増える」となりがちですが、AI技術の進歩に伴い、同じ仕事を圧倒的に少ない人数で回せるケースが増えています。リソースを拡大する前にAIで自動化できる部分を探し、むしろ創造的な仕事や新プロジェクトに人材を振り向ける——この発想にシフトすることで、組織全体の生産性は飛躍的に高っていくことが考えられます。
6. 「全員」とは、本当に全員を意味する
メモの最後では、「これはCEOや役員を含めた“全員”が対象だ」と明記されています。経営陣などのトップを含めた全社員が、AI活用について学び実践し続ける姿勢を持つことが不可欠というわけです。
まとめ:「AI時代」に変わり続ける組織こそが勝者になる
Shopifyが掲げる6つの方針は、単なる“AI推進”を超えて「組織としてAIを共生させる」ための具体的なアクションを提示しています。そこには、評価制度への組み込みやプロトタイプ段階での活用、リソース配分の見直しなど、多角的なアプローチが詰まっています。
経営者の立場から見ると、「新規ツールをどう導入するか」ではなく、「社員一人ひとりの思考と行動様式にAIが根づくにはどうすればよいか」を考えることが最重要テーマになるでしょう。トップから現場まで、一丸となってAIを使いこなし続ける組織こそが、これからのビジネスをリードする存在になるはずです。
- この記事にいいね!する
この記事を書いた人

稼働ステータス
◎現在対応可能
- Taishin Murase
職種
コンサルタント
ITコンサルタント
希望時給単価
5,000円~10,000円
【経歴】 千葉大学工学部→千葉大学院卒業 →新卒で楽天グループにエンジニア入社。エンジニア兼PMとして主に物流システムの開発 → 株式会社Adeviaを創業。 約5年間の大規模システムの開発経験、3年間のPMの実務経験があります。要求・要件定義から、設計・実装・テスト、チームのマネジメント経験があります。
スキル
Python
Java
React
・・・(登録スキル数:9)
スキル
Python
Java
React
・・・(登録スキル数:9)