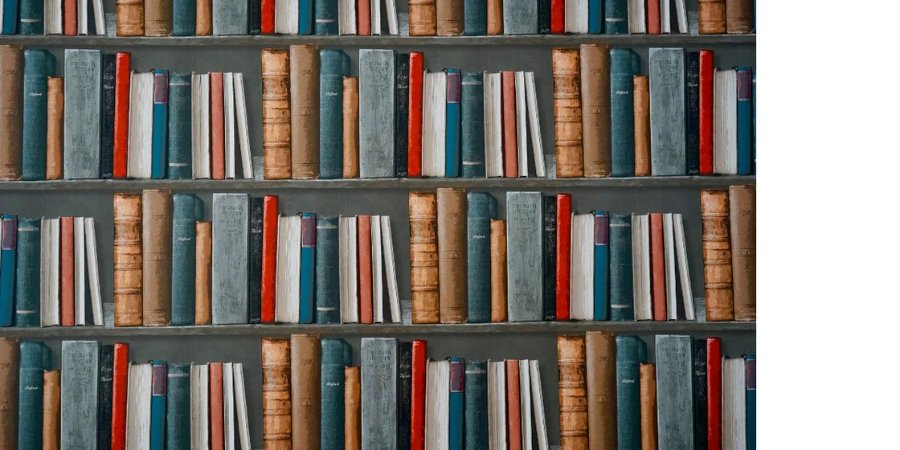テレアポの生産性を短期的に引き上げるにはリスト戦略が有効
- 荒井 和也
- 記事制作日2025年3月18日
- 更新日2025年3月18日
- 0いいね!
この記事は、テレアポでなかなか結果が出ずに課題を持っている方、新規顧客開拓のテレアポ部署や営業部署の管理者の方などが対象です。ここではB2Bを主にして解説してあります。
テレアポでなかなか結果がでない、そういった方は多くいるだろう。
実際、自分も営業時代、テレアポ漬けの毎日だったが、なかなか結果が出なかった。
もともと営業が苦手であり、トークも苦手、そんな私でもなんとか営業部のお荷物にならないよう、テレアポで結果を出そうと粘っていたが、その時に工夫したのたテレアポのリストである。
リストが良ければ、営業力やトークが苦手でもアポは入るし、受注にもつながるのだ。
もちろん、最低限の営業力やトークは必要だが、その実力が他者より劣っていたとしても、リストの工夫次第で、結果を出せたりもするのだ。
実はこういったことがきっかけで、数年後には、営業リストや営業管理システムの責任者を任されることになった。営業部からも頼りにされる人になれた。
テレアポはトークも重要だが、それと同じくらいリスト戦略も重要である。
ということで、さっそくテレアポの生産性を引き上げるリスト戦略について語っていこうと思う。
まず、そもそもテレアポとはテレフォンアポイントメントの略である。
電話で相手から商談時間の約束を取り付けるのがテレアポのゴールである。
とはいえ、営業部としては、商談時間の約束を取り付けるのがゴールではない。
ゴールは受注することである。厳密にいえば、受注というよりも、会社への入金が営業部としてのゴールである。
当然、お客様の立場であれば、お金を払って終わりではない。
そこから商品をを利用し、結果を出して満足してもらうまでがゴールである。
お客様から言えば、入金はあくまでスタートあることは念のため伝えておく。
話は戻って、テレアポの最終ゴールとは、営業部目線でいえば、受注(あるいは入金)がゴール(本当のゴールは満足してもらうことだがここでは受注までとする)であり、商談の時間を頂くこと(アポイント)は最終ゴールではない。
テレアポという言葉自体で捉えると、商談の時間を頂くまでがゴールとなるが、結局、商談がたくさん入っても受注ゼロでは会社としては意味がないのだ。
よってリスト戦略とは、アポイントが取りやすいリストというよりも、受注(入金)しやすいリストのほうが優先度としては高くなる。
(ただし、勘違いしてほしくないのは、最初から受注を狙って、アポイントは二の次という考えだとかえって伸びない。最初はアポイントまでがゴールでいい。アポイントを取ることに慣れてきたら、受注をゴールに据えると良い。まずは現場の感覚をつかむことが重要だ)
では、受注しやすいリストとは何なのか?
その答えは、既に自社の商品を利用しているお客様の中にある。
さらに言えば、自社の商品を利用して、満足しているお客様だ。
まだお客様がいないのであれば、同業他社のお客様を参考にするといいだろう。
お客様とはどういったお客様かを紐解くのがリストの正解にたどり着きやすい。
お客様の会社の規模は?業種は?業歴は?商品は?サービスは?エリアは?代表はどんな人か?
一言で言えば属性である。
こういった情報を紐解き、それに似たようなリストを集めるのがまずは重要である。
つまりは、探すリストとは、自社の商品と相性が良い属性のターゲットということになる。
商談において、商談相手は自社と似たようなお客様の成功事例を気にするものだ。
そもそも、商談相手自体が自社の成功事例と似たような属性の会社であれば、成功事例も説明しやすいし、相手も納得しやすい。つまりは受注につながりやすいのだ。
だからこそ自社のお客様と似たような属性のリストが相性が良いのだ。
これでリストの会社規模や業種、エリアなどといった属性は決まるだろう。
次に重要なのはタイミングである。
一生懸命、電話をかけてアポイントを取ったとしても、既に他社の商品を買ったばかりであれば、受注は厳しいだろう。
ちょうど、そういった商品の購入を検討していた、いい商品がないか探していた、買い替え時期だった、そういったタイミングの良いリストであることが重要だ。タイミングは受注において大事な要素だ。
次にそれと同等に重要なのはお金である。
いくら商品を気に入ってもらったとしても、予算がないのでは受注にはつながらない。
自社の商品を買ってもいいくらい予算を持っているか、予算のあるリストであることも重要だ。予算がないのに、無理くり売ったとしても、クレームになる確率は高くなる。予算に余裕のある会社であることも重要な要素だ。
そして最後に決裁者へのつながりやすさである。
アポイントメントは基本的に決裁者にとる。
その商品を買うか買わないか、判断・決裁できる人だ。
規模の小さい会社であれば、基本的に社長になる。
その商品がいいか悪いか、買うか買わないか判断できない人に、いくらテレアポでトークをしても理解はしてもらえない。門前払いされてしまうのがオチだ。アポイントが取れて、商談しても、いい話ありがとう、で終わってしまう。購入にはつながらない。
よって、リストとしては決裁者につながりやすいリストが望ましい。
まとめると次のようになる。
①自社の商品を利用しているお客様と似たような属性のリスト(会社規模・業種・業歴・商品、サービス・エリア・代表の人柄など)
②商品購入のタイミングが良いリスト(売りたい商品未導入、検討中、買い替え時期など)
③商品を買えるだけの予算がある(お金がある)リスト
④商品購入のジャッジができる決裁者につながりやすいリスト
これらが揃っているのがいいリストということになる。
■リストの探し方
次にリストの探し方であるが、
①自社の商品を利用しているお客様と似たような属性のリスト(会社規模・業種・業歴・商品、サービス・エリア・代表の人柄など)
であれば、実際のお客様の会社名・電話番号などでGoogle検索すると、似たような会社のまとめサイト等がでてくるので、それがリストの一つの指標になる。
そして、そこで出てきた自社のお客様と似たような会社で、また会社名・電話番号などで検索するとさらに別のまとめサイト等が出てきたりする。
こんな感じで、芋づる式にリスト対象を増やすことができる。
②商品購入のタイミングが良いリスト(売りたい商品未導入、検討中、買い替え時期など)
商品未導入や検討中であれば、まだ会社やお店ができて間もないリストであれば、商品導入はされていないことが多いので、そういったリストが一つの指標になる。
他社の商品を既に利用しているのなら、その商品はいつから導入しているかが分かれば、商品の買い替え時期、あるいは、商品を使ってみて、自社には合わないと分かった時期などタイミングがつかめれば(半年後・1年後・数年後など)、タイミングが良いリストになるだろう。
③商品を買えるだけの予算がある(お金がある)リスト
これはその会社の従業員がどのくらいいるかが一つの指標になる。外部委託やパート・アルバイトではなく、正社員が一つの指標だ。
正社員がいるということは、毎年必ず、最低数百万以上の出費があるということである。言い換えれば、そのくらい予算が出せる会社ということだ。自社の商品にその正社員と同じくらいの価値があり、さらに人件費より安ければ、予算も納得してもらいやすいだろう。
毎月数万円程度の費用であれば、正社員ゼロの会社でも予算は出せるところもあるが、毎月数十万円程度の商品・サービスとなると、正社員がいない会社だと予算的に厳しい会社が多くなる。
このあたりの予算の規模は、自社の商品の料金体系によって異なるので、それに合った規模のリストを探してほしい。
④商品購入のジャッジができる決裁者につながりやすいリスト
これは単刀直入に言ってしまえば、決裁者の携帯番号が分かればベストである。なければ、会社の電話に電話して、受付突破して決裁者と話すしかない。
当然、規模が小さい会社のほうが、決裁者とはつながりやすいし、規模が大きい会社は決裁者とはつながりにくくなる。
とはいえ、これだけのリストを自分一人で探したり、作り上げるのも限界はあるだろう。そこでリスト会社やリスト作成ツールなどの出番となる。
世の中の情勢は日々変化している。ターゲットの会社も日々変化しているのだ。
なので、リストというのは鮮度も大事になる。
今は、タイミングばっちりというリストも1ヶ月後にはタイミングが悪いリストにもなりうる。
こういった状況の中で、この①~④まですべて揃ったリストというのは、なかなか見つからないだろう。
しかし、①~④の範囲である程度のところまで揃えることは可能だ。
それをするだけでも、生産性は大幅に変わってくるだろう。
また、経験が蓄積されていくと、リストの揃え方も上手になってくるのだ。
リスト戦略はテレアポにとって、とても重要なので、①~④を意識して、テレアポのトークやトークスクリプトとともに、リスト戦略にも取り組んで欲しい。
最後に宣伝になるが、私はこういった経験をもとに、営業リストを追求して、独立までしてしまった。
この①~④にこだわったリストを日々追求している。
営業リストについて相談したい人は、下にあるリンクから、問い合わせ、お待ちしております。
- この記事にいいね!する
この記事を書いた人

- 0いいね!
稼働ステータス
△仕事内容による
- 荒井 和也
職種
その他
その他
希望時給単価
5,000円~10,000円
埼玉県でフリーランスとして活動。 2002年新卒でシステムエンジニアとして都内SI企業入社し、エンジニア従事後、ホームページ制作販売会社へ転職。 テレアポ・新規営業経験後、アルバイトスタッフの管理業務、コールセンター立ち上げ等を経て、リスト戦略の責任者を経験。 新規開拓用の営業リスト・営業管理システムの設計、リリース、運用保守を経験。リストからの月間受注数60件以上を創出。 その後、新会社立ち上げメンバーを経験。のち2020年に独立。 取引実績30社以上。 ■お問い合わせ こちらをクリックしフォームからお問い合わせください。
スキル
Microsoft Excel
Python
HTML/CSS
スキル
Microsoft Excel
Python
HTML/CSS