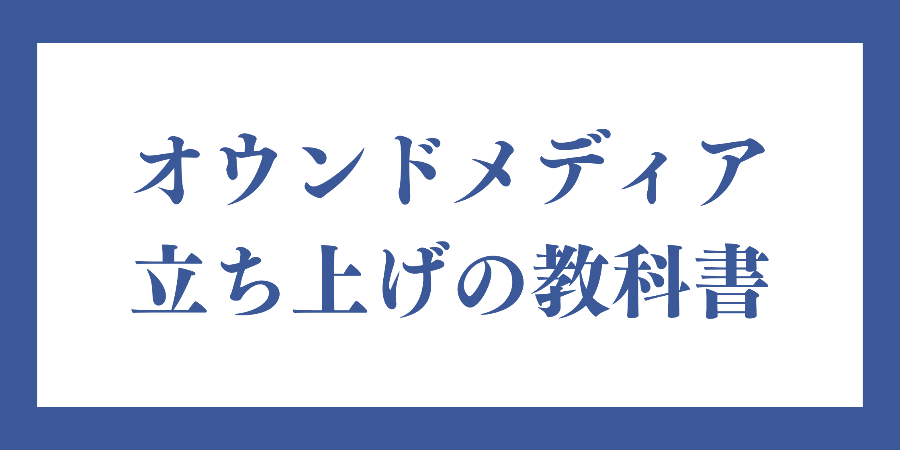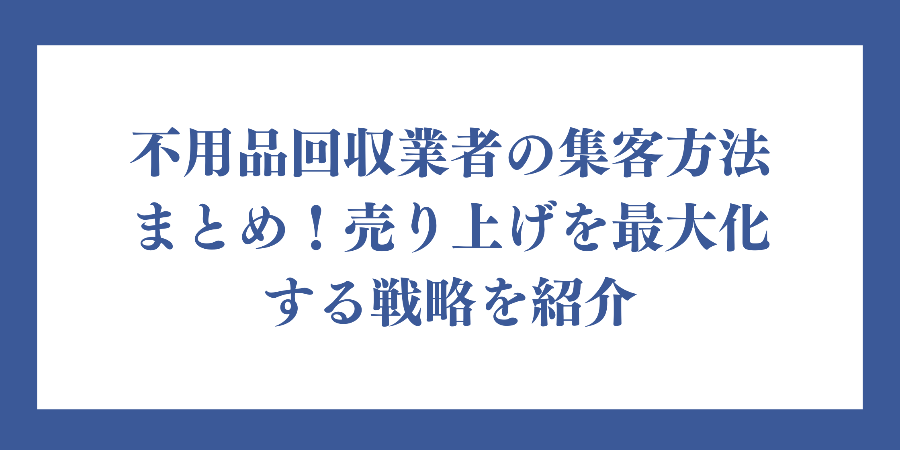【CRO対策】SEOだけやって何になるんですかw
- 堀 碩信
- 記事制作日2025年2月7日
- 更新日2025年2月16日
- 1いいね!

SEO対策の会社はたくさんありますが、結局SEOはアクセス数を増やすということが主目的になっているので、アクセスの割に問い合わせが増えないということは起きがちです。
ビジネスの売り上げを考えたときに、SEOでアクセスを増やした後にどれだけ問い合わせ、購入を増やせるかが実際には大切になります。
そこで、考えてほしいのがCROです。CROはコンバージョン率最適化のことで、獲得したアクセスをどれだけCVに転換できるかという指標になります。
今回はCROについて解説します。
SEO×CROが最強です
SEOとCRO(Conversion Rate Optimization)を組み合わせることで、集客からコンバージョンまでの一貫した最適化が可能になります。
SEOで質の高いトラフィックを獲得し、CROでそのトラフィックを効率的に成果へと転換することで、マーケティング効果を最大化できます。
結局SEOが得意でアクセスが増やせるものの、CV増やすのは苦手という会社が多数です。
CROはSEOとは別の考え方が必要になるので、ここからはCROの考え方と施策を紹介していきます。
CROの考え方
ユーザー行動をファネルに分解する
ユーザーの行動プロセスを「認知」「興味」「検討」「購買」などの段階に分け、各段階での行動を詳細に分析します。これにより、どの段階でのつまずきが多いのか、どこに改善の余地があるのかを明確に把握することができます。
それぞれの段階に該当するコンテンツはどれかを自社のコンテンツの中から考えるというのが、最初のステップです。
BtoBであればブログコンテンツは認知段階にあたり、サービスコンテンツは興味、料金ページは検討などに該当するでしょう。
ファネルごとの転換率を算出する
各段階での離脱率や遷移率を数値化し、改善が必要なポイントを特定します。
例えば、商品ページから問い合わせフォームへの遷移率が低い場合、その間のユーザー体験を重点的に改善する必要があります。
ここでのデータはGA4などから見ることができます。具体的には、探索のファネル分析という部分があるので、そこで転換率を見ていきましょう。
CVR向上の施策を洗い出す
どの部分に課題があるかということが分かったら、それぞれにおいてCVR向上の施策を洗い出しましょう。
この時点では思いつく限り、できるだけ多く施策を出していくことが必要です。
次の章で具体的なCROの施策を出しているので、それを参考にそれぞれのページにおいてできるCRO施策を出していきましょう。
PIEフレームワークで優先順位をつける
改善施策の優先順位を決定する際は、PIEフレームワーク(Potential:改善効果、Importance:重要度、Ease:実装の容易さ)を活用します。
限られたリソースを効率的に活用するため、効果が高く、実装が容易な施策から着手します。
計測環境を整える
正確なデータ収集と分析のために、適切な計測環境を整備します。具体的には以下があります。
- アナリティクスの設定
- ヒートマップツールの導入
- A/Bテストの環境構築
- コンバージョン計測の設定
あのデータが欲しかったけど、計測していなかったなどになってしまうとデータを取るのに、さらに時間がかかってしまうので、この辺りは最初にしっかりと設計しておく必要があります。
PDCAを回す
施策の実施後は、効果を測定し、次の改善につなげます。継続的な改善サイクルを回すことで、徐々に最適化を進めていきます。
CROは一度やったら終わりではありません。一度やった手法がどれだけ効果が出ているのかをチェックすることで、さらに次の施策につなげやすくなります。
CROの具体的な手法
ここではCROの具体的な手法について紹介していきます。
固定フッターにCTAを設置する
スクロールしても常に表示されるCTAを設置することで、ユーザーがいつでもアクションを取りやすい環境を作ります。
特にモバイルでは、画面下部の固定CTAが効果的です。LINE、メール、電話などCVポイントが複数ある場合は、すべて入れたくなってしまうかもしれませんが、ユーザーを迷わせないためにも一つに絞ることが重要です。
ファーストビューにCTAを設置する
ファーストビューにCTAを配置することで、即座にアクションを促すことができます。
この際に、ページの内容がどの層に向けたものなのか、どのような流入経路から入ってきているのかによって、CTAの内容を変える必要があります。
例えば、リスティング広告からの流入がメインのページであれば、トップページに
ハードルの低いCVポイントを設置する
メインのコンバージョン(商談申し込みなど)だけでなく、資料ダウンロードやメルマガ登録など、比較的気軽に実施できるCVポイントも用意します。
BtoCの場合だと、見積もりシミュレーションやLINE登録などがCVポイントとしてはよくあります。
離脱ポップアップを設置する
ユーザーが離脱しようとするタイミングで、最後の訴求を行うポップアップを表示します。ただし、過度な使用はユーザー体験を損なう可能性があるので注意しましょう。
ユーザーがどのページで離脱したのかなどによって、ポップアップの内容を変えることで、ユーザーに適した訴求をできる可能性があります。
例えば、問い合わせフォームまで到達したのに離脱した場合は、フォーム入力が面倒だった可能性もあるので、電話問い合わせの訴求をするなどが考えられます。
クリエイティブとファーストビューの一貫性を保つ
広告やソーシャルメディアから流入したユーザーが期待する情報と、実際のランディングページの内容を一致させることで、離脱を防ぐことができます。
特にディスプレイ広告などの場合は、バナーをテストしているうちにLPのファーストビューと訴求がずれてしまうことがあります。
そのような場合は、バナーかファーストビューの訴求を変えて一貫性を保つようにしましょう。
CTAエリアにマイクロコピーを追加する
CTAボタンの周辺に、不安を解消するメッセージや価値提案を追加することで、クリック率を向上させます。
マイクロコピーの内容としては、「今すぐに行動する理由」「安心感を与える」「不安を解消する」などがあります。
どの訴求がいいのかは、サイトのタイプやコンテンツのタイプにもよりますので、文脈に合った訴求を使うようにしましょう。
ブログページのCTAを自然なテキスト導線にする
ブログコンテンツの流れに沿った自然な形でCTAを配置することで、ユーザーの抵抗感を減らします。
ブログコンテンツでのCTAはバナーや定型的なCTAになりがちですが、コンテンツの文脈に沿っていないCTAはクリック率が低く、問い合わせにはつながりにくい傾向にあります。
そのブログを読んでいる読者のことを想像して、今どのようなサービスを求めているのかを理解することで自然なCTAを設置することができます。
問い合わせフォームの入力項目を最小限にする
必要最低限の項目のみを残すことで、フォーム入力の心理的ハードルを下げ、完了率を向上させます。
EFOと呼ばれる領域ですが、ここがしっかりできていない会社は意外と多いです。
簡単であり、かつインパクトの大きいところなので、まずはここから開始しましょう。
コンテンツSEO×CROが得意です
1記事3万円~対応可能ですので、コンテンツSEOの外注先を探している方はぜひ一度ご連絡下さい。
戦略立案からキーワード選定、記事の設計、ライティング、内部リンク戦略など、コンテンツSEOにかかわることでしたら、なんでもご相談ください。
無料でSEOの診断も行いますので、気になる方はぜひご連絡ください。
chatwork:32nobu
メール:m.hori@delta-web.co.jp
- この記事にいいね!する
この記事を書いた人

- 104いいね!
稼働ステータス
◎現在対応可能
- 堀 碩信
職種
マーケティング
Webディレクター
希望時給単価
3,000円~5,000円
【経歴】 京都大学文学部卒業。在学中から観光産業への興味を深め、2019年に観光テック企業のツアーベース株式会社に参画。同社では主力事業である観光物流事業のWEBマーケティングを統括し、新規事業として立ち上げた引越し事業でもマーケティング責任者として成果を創出。 2020年10月に独立。WEBコンサルタントとして複数の企業のマーケティング戦略立案、実行支援に従事。特にBtoBマーケティング、リードジェネレーション、SEO戦略の領域で支援実績を重ねる。 2021年6月、デジタルマーケティング支援を手がける株式会社deltaを設立、代表取締役に就任。20社以上のクライアントの事業成長を支援している。WEBマーケティング戦略の立案から実行支援、社内体制の構築まで、包括的なサポートを提供。 得意領域は①SEO対策②MEO対策③リスティング広告の3つ。 https://delta-web.co.jp/ 【実績】 ・関西エリアの不用品回収会社様 ご依頼内容:飛び込みで集客していたが、WEBでの集客を始めたい 施策:まずはすぐに結果のでるリスティング広告から始めることを提案。 不用品回収業者は悪質業者が多いことから、安心・安全を訴求したLPを作成しリスティング広告を開始。 結果:CPA1500円で毎月の問い合わせが30件達成 ・関西エリアの引越し業者様 ご依頼内容:リスティング広告からの売上があまり上がらない。 またSEO対策を行ってリスティング広告の予算を減らしたい。 施策:リスティング広告の予算を少しずつ減らしながら、SEOの記事作成を開始。 結果:リスティング広告はターゲットを単身から家族へ変更することで売上向上。 またCPAも5000円から3000円まで低下。 SEO対策は開始から1年で2万PVを達成し、月間の問い合わせ数が5〜10件継続的に発生。 ・東京の不用品回収業者 ご依頼内容 ・大阪の外壁塗装業者
スキル
SEO
リスティング広告
LPO
・・・(登録スキル数:11)
スキル
SEO
リスティング広告
LPO
・・・(登録スキル数:11)