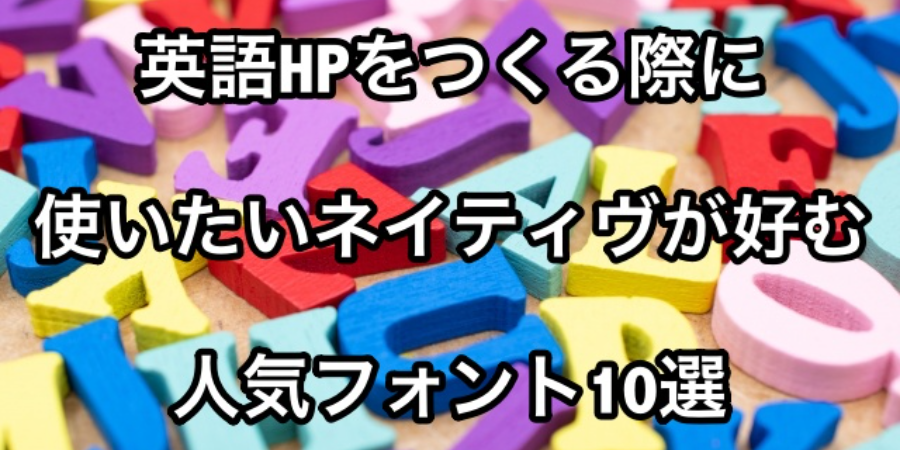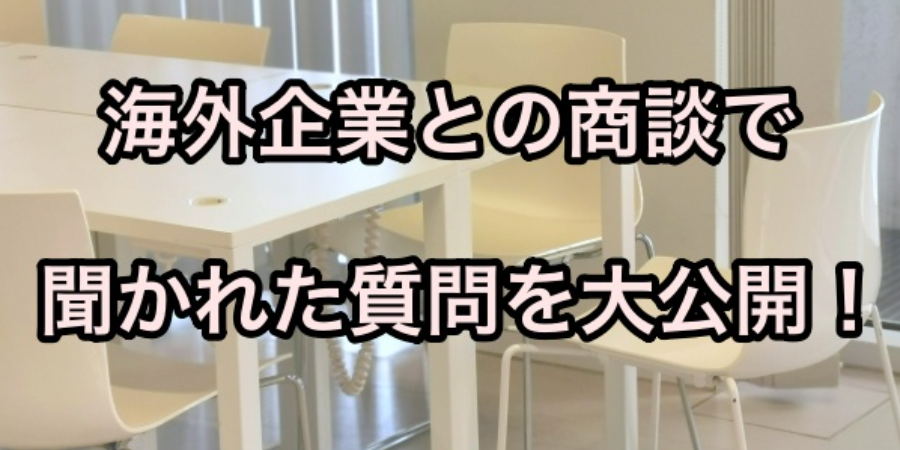企業のキャッチフレーズを自動翻訳してみた結果
- 桝村 翼
- 記事制作日2025年9月3日
- 更新日2026年1月6日
- 34いいね!

近年、AI(Artificial Intelligence / 人工知能)技術の進展により、翻訳についても自動翻訳やAI翻訳を使う人々が増えてきました。
知名度のある企業においても、コスト削減などで翻訳業務をAIに任せてしまう企業も少なくありません。
しかし、AIに任せっきりにしてしまうと、時に大きなトラブルや損害につながることもあります。
たとえば、私たちが消費者の立場でよく目にする企業のキャッチコピー。
企業のブランドイメージを創り上げる、非常に重要な言葉です。
しかし、このキャッチコピーをAIや自動翻訳に任せっきりにすると、とりかえしのつかない、とんでもない間違いを犯してしまうことがあります。
本記事では、主に企業名、企業のキャッチコピーを事例に翻訳の失敗事例を取り上げ、人が行う翻訳がいかに重要かを考えます。
この記事を読むことで自動翻訳やAIによる翻訳に頼りきりになる危険性に気がつき、失敗を防ぐためのポイントについても知ることができます。
ぜひ、参考にしてください。
ブランドイメージを損ないかけた有名な誤訳の事例
AIや自動翻訳がない時代においても、翻訳の失敗事例はたくさんありました。
それら失敗の多くは、翻訳先の言語や文化を深く考えることなく訳してしまったことが原因です。
それでは、歴史的に有名な企業の翻訳失敗例をまずは見てみましょう。
ペプシ・コーラ(Pepsi-Cola)
ペプシ・コーラのキャッチコピーで「Come alive with the Pepsi Generation」というものがありました。
これは「ペプシの世代で生き生きと」と言う意味です。
しかし、これを台湾語に翻訳した際に「ペプシは先祖を死からよみがえらせる」となってしまいました。
おそらく、「come alive」を「よみがえる」、「generations」を「先祖」と認識してしまったのでしょう。
ペプシ・コーラに不気味かつ侮辱的な印象を与えてしまったようです。
ケンタッキー・フライド・チキン(Kentucky Fried Chicken)
ケンタッキー・フライド・チキンのスローガンで「finger-lickin’ good」というものがありました。これは「指をなめたくなるほど美味しい」という意味でしたが、中国語に訳された時にはなぜか「指を食いちぎる」というように翻訳されてしまいました。
ケンタッキー・フライド・チキンは中国人に「野蛮」というイメージを持たれてしまったそうです。
クアーズ・ビール(Coors Beer)
ビールメーカーのクアーズのキャッチコピーに「Turn it loose」というものがありました。
これは「クアーズのビールは気持ちを楽にさせる」とか「クアーズのビールはあなたをリラックスさせる」という意味を込めたものでした。
しかし、これをスペイン語に翻訳したところ、なんと「下痢になる」と認識されてしまいました。
確かに「Turn it loose」には「ゆるくする」という意味もあるので、誤解が生じてしまったのでしょう。
日本語の場合は特にそうなのですが主語がないキャッチコピーには気をつけなければいけません。
アメリカン航空(American Airlines)
アメリカン航空はいっとき革張りのシートを導入しました。
その時の宣伝文句が「Fly in Leather」です。
つまり、「革で飛ぼうよ」というキャッチコピーでした。
しかし、これをメキシコの利用者に向けて発信したところ、「裸で飛ぼうよ」と翻訳されてしまったようです。
ゼネラルモーターズ(General Motors)
アメリカの歴史ある自動車メーカー、ゼネラルモーターズが、「シボレー・ノヴァ(Chevrolet Nova)」を南米で発売しようと試みたことがありました。
しかし、販売台数が思うように伸びなかったそうです。
その理由は、スペイン語で「行かない」を「no vas」と言うからだったのです。
つまり、「シボレー・ノヴァ(Chevrolet Nova)」は「どこにも行かないシボレー」と解釈されてしまったのです。
フォード(Ford)
もう一つ、アメリカの歴史ある自動車メーカー、フォードの話です。
1970年代にピント(Pinto)と言う車を発売し、これをブラジルでも売ろうと試みました。しかし、ゼネラルモーターズの「シボレー・ノヴァ(Chevrolet Nova)」と同様に、販売台数は思うように伸びません。
調べてみると、「ピント(Pinto)」は、ブラジルの俗語で「小さな男性器」という意味だったのです。
確かに「Pinto(小さな男性器)に乗ってる」とは言いたくないですよね。
シュウェップス(Schweppes)
シュウェップスがイタリアでトニックウォーターを売り出そうとした時のことです。
なぜか、キャンペーン広告が「シュウェップスのトイレットウォーター」と翻訳されてしまったそうです。
トイレの水、飲みたくないですよね。
パーカー・ペン(Parker Pen)
1888年創業の日本人にとっても有名なペンメーカー、パーカーペン。
高品質な筆記具で広く知られており、日本人でもパーカーのペンを使っていると一目置かれることもあるペンです。
ある時、パーカー・ペンは「It won’t leak in your pocket and embarrass you」というキャッチコピーを掲げていました。
これは「ポケットの中でインクが漏れることなく、恥ずかしい思いをすることはありません」という意味でした。
しかし、このキャッチコピーを使って、メキシコでの販促キャンペーンに乗り出したところ、「ポケットの中で液が漏れて、妊娠することはありません」と翻訳されてしまったのです。
これは、英語の「恥ずかしい思いをさせる」という意味の単語「embarrass」を、スペイン語で「妊娠させる」という意味の「embarazar」と混同してしまったことが原因でした。
高級ペンのイメージがメキシコでは一気に失墜してしまったようです。
近畿日本ツーリスト
日本でもかなり有名な旅行会社近畿日本ツーリスト。
この会社が、そのままの名前で英語圏に進出したらとんでもない誤解が生じてしまいました。
当時の、近畿日本ツーリストの英語表記は「Kinki Nippon Tourist」でした。
しかし、英語圏に進出した直後は、性的行為を体験するツアーの依頼が相次いだそうです。
どうやら「Kinki Nippon」の二つ目の単語の最初の「N」が最初の単語の「Kinki」と結びついてしまい「Kinkin Ippon Tourist」と解釈されてしまったようです。
もっと悪いことに、ここからさらに「Chin Chin Ippon Tourist」と解釈する人もいたようで、性的体験ツアーを主に販売する旅行会社という誤解を与えてしまったようです。
ここまで紹介してきた事例は、誰もが知っている有名企業の翻訳ミスです。
有名企業でこれだけ翻訳ミスがあるということは、中小企業であれば、もっとたくさん誤訳があり、企業のイメージを失落させてしまった例は星の数ほどあると予想されます。
それでは、次のセクションでは、日本の企業のキャッチコピーをそのまま自動翻訳するとどうなるのかを検証してみましょう。
日本企業のキャッチフレーズを自動翻訳してみてうまく翻訳できた事例 10選
自動翻訳やAIを使った翻訳は必ずしも全てが間違いということではありません。
中には、「お、うまく訳されてるな」と思わせるものもあります。
このセクションでは、日本企業のキャッチフレーズを自動翻訳にかけてみた結果の良い事例を紹介します。
三越伊勢丹ホールディングス:向き合って、その先へ
百貨店の老舗、三越と伊勢丹を経営する三越伊勢丹ホールディングス。
この企業のキャッチフレーズは「向き合って、その先へ」です。
さて、これを自動翻訳した結果が以下です。
Face it and go beyond
英語にしても、なかなかいいキャッチフレーズではないでしょうか。
株式会社東芝:人と、地球の、明日のために
日本を代表する電機メーカーの東芝。この企業のキャッチフレーズは「人と、地球の、明日のために」です。
これを自動翻訳した結果が以下です。
For the future of people and the planet.
日本語でもストレートフォワードで読んで字のごとくというようなキャッチフレーズなので、自動翻訳をしてもわかりやすいですよね。
株式会社クボタ:壁がある。だから、行く
トラクターなどの農業機器を扱っている日本を代表するメーカー、クボタのキャッチフレーズは「壁がある。だから、行く」です。
これを自動翻訳したものが以下です。
There's a wall. So, I go.
かつて、イギリスの登山家ジョージ・マロリーは「なぜ、エベレストに登るのですか?」と聞かれて「そこにあるから(Because It’s there)」と答えたそうですが、そのニュアンスと似ていますよね。
なので、世界的にもこの表現は受け入れられやすいかもしれませんね。
キユーピー株式会社:愛は食卓にある。
マヨネーズで有名なキューピー。
この会社のキャッチフレーズは「愛は食卓にある」です。
もちろん、「食卓は栄養を摂取する場所だけではなく、愛を育む場所である」という意味が込められていますが、ここでいう「愛」は「マヨネーズ」そのものを指しているとも考えられます。
つまり、食卓においてあるマヨネーズにたくさん「愛」が詰まっているという解釈もできますよね。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると以下のようになります。
Love is at the dinner table.
これも、素直に伝わる誤解されにくい訳文ですよね。
サントリーホールディングス:水と生きる
アルコール飲料や清涼飲料水を製造しているサントリー。
この会社のキャッチフレーズは「水と生きる」です。
飲料を作っている会社なので、良質な水がなければ生きていけない会社であり、自然環境にも気を配っているという気持ちが伝わるキャッチフレーズです。
そして、また消費者である私たちにも「水と一緒に生きていかなければいけないでしょ」と呼びかけているようにも聞こえます。
この、キャッチフレーズを自動翻訳したものが以下です。
Living with Water
そもそもの日本語が、非常にシンプルでわかりやすいので、英語にしても通じ安いキャッチフレーズですよね。
株式会社NTTドコモ:あなたと世界を変えていく
日本の携帯電話会社の大御所NTTドコモ。
iモードをはじめ、携帯電話業界において数々のイノベーションを起こしてきました。
特にNTTドコモが提供するアプリケーション開発の特徴は短期間でアプリケーションを開発して公開し、利用者の利用体験を徐々に向上させていくというものです。
この手法がキャッティフレーズ「あなたと世界を変えていく」に現れていると思いませんか?
さて、このキャッチフレーズを自動翻訳したものが以下です。
Changing the world with you.
こちらも素直なひねりのないメッセージなので、自動翻訳をしてもわかりやすい表現になっていますよね。
株式会社リクルート:まだ、ここにない、出会い
求人広告、人材紹介を事業の中核に据えて、ITソリューションなど幅広い事業を展開しているリクルート。
こちらの会社のキャッチフレーズは「まだ、ここにない、出会い」です。
日本語で聞いても「うーん、なかなかうまいこと言うな」と感心させられるキャッチフレーズですよね。
正直なところ、このキャッチフレーズを自動翻訳すると意味不明な翻訳が出てくるのではと予想しましたが、なかなか良い結果が生成されました。
An encounter that hasn't happened yet.
いかがでしょうか?
まだ、起きたことのない出会いを演出してくれる会社のイメージが伝わってくるキャッチフレーズになっていないですか?
株式会社ニトリホールディングス:「お、ねだん以上」
お手頃な価格で良質な家具や雑貨、家電を提供しているニトリ。
こちらのキャッチフレーズはコマーシャルでもよく聞く「お、ねだん以上」です。
株式会社リクルートのキャッチフレーズと同様、このキャッチフレーズを自動翻訳するのは、なかなか難しいのではと思っていましたが、以下のような結果が生成されました。
More than you'd expect.
直訳すると「期待以上」となりますが「この値段で買ったのに期待以上だった」と言う思いが十分伝わってくる、原文に込められた気持ちからほとんどズレのない訳文に仕上がっていると思いませんか?
ユニ・チャーム株式会社:やさしさをつくる。やさしさでささえる
ベビーグッズや高齢者を対象とした介護用品、ペット用品を製造している会社ユニ・チャーム。
人にとって大切な人やペットが快適な生活を過ごせるようなグッズを提供していますよね。
そんな会社のキャッチフレーズは「やさしさをつくる。やさしさでささえる」です。
人にやさしい製品をつくって、その製品で人の生活をささえると言う気持ちが率直に現れているように思えます。
このキャッチフレーズを自動翻訳した結果が以下です。
Creating kindness. Supporting with kindness.
原文でやさしさが強調されている通り、自動翻訳をしてもkindnessが強調され、しかも語呂の良い感じのキャッチフレーズが生成されました。
第一三共株式会社:イノベーションに情熱を。ひとに思いやりを
医薬品の研究開発を行っている第一三共株式会社。
この会社のキャッチフレーズは「イノベーションに情熱を。ひとに思いやりを」です。
このキャッチフレーズを自動翻訳した結果が以下です。
Passion for innovation. Compassion for people.
PassionとCompassionが同じような音で韻を踏み、語呂的にもなかなかいいものに仕上がったと思いませんか。
さて、このように自動翻訳を使った場合でもなかなか良いキャッチフレーズの翻訳が生成されることがわかりました。
しかし、成功事例だけに注目してしまうと、大きな落とし穴に落ちてしまう可能性もあります。
次のセクションでは、自動翻訳をしてみたらイマイチな結果となってしまった日本企業のキャッチフレーズの事例を紹介したいと思います。
日本企業のキャッチフレーズを自動翻訳してみた結果、イマイチだった事例 10選
日本企業のキャッチフレーズを自動翻訳してみた結果、比較的多くの企業のキャッチフレーズがイマイチな結果となってしまいました。
その理由は、1)気持ちが入り込みすぎている、2)言葉遊びがある、3)比喩的表現があるなどです。
このような場合には、企業の真意を理解してキャッチフレーズを作り上げる必要があるでしょう。
それでは、イマイチだった事例を10個紹介したいと思います。
株式会社ロッテ:お口の恋人
ガムを主流としたあらゆるお菓子を製造しているロッテ。
この会社のキャッチフレーズは1958年から使われている有名な「お口の恋人」です。
これを自動翻訳にかけると「lover of the mouth」となりました。
これはこれでいいのかな、とも思うのですが、この表現だとなんか可愛らしさがありませんよね。
せっかく甘いお菓子を提供しているので、「Your mouth's Sweetheart Lotte」とか「Sweetheart for your mouth Lotte」などの方がいいかもしれませんね。
株式会社ファンケル:もっと何かできるはず
ファンケルは化粧品、健康食品、サプリメントを製造販売している会社です。
この会社のキャッチフレーズは「もっと何かできるはず」です。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると「There must be something more we can do」となりました。
間違ってはいないと思うのですが、このキャッチフレーズの真意は「あなたの健康、美しさのために私たちはもっと何かできるはず、と日々考えています。でも、あなたも自分自身に何ができるかを考えてみてください。ほら、私たちの製品がありますよ」ではないでしょうか。
となると、「There must be something more we can do」よりは「There must be something more we can do and you can do」の方がいいのかな、などと思いました。
小林製薬株式会社:あったらいいなをカタチにする
医薬品、芳香剤、衛生材料を製造販売する小林製薬。
この会社のキャッチフレーズは「あったらいいなをカタチにする」です。
このキャッチフレーズを自動翻訳で翻訳すると「Making your dreams come true」となりました。
確かに意味的には間違ってはいませんが、これではありきたりで、つまらないキャッチフレーズになってしまっています。
日本語であえて「あなたの夢をかなえます」と言っていないのだから、英語でも日本語のニュアンスを残したいですよね。
そのように考えると「What you want, What we make」とか「What you want, What we shape」などとした方がいい感じがします。
株式会社JTB:感動のそばに、いつも
国内、海外のパッケージツアーなどを販売するJTB。
JTBのキャッチフレーズは「感動のそばに、いつも」です。
これを自動翻訳すると「Always beside the emotion」となりました。
確かに間違いではないのですが「感動のそばに、いつも」という言葉の中には、私たちがあなたの感動を演出しますよ、プロデュースしますよ、と言う意味もあるのではないかと思うのです。
そのように考えると「We will always be there for your excitement(あなたの感動のために、いつもそばにいます)」の方がよいかもしれませんね。
東日本旅客鉄道株式会社が発行している「Suica」:日本を、一枚で
「Suica(スイカ)」とは、東日本旅客鉄道(JR東日本)が発行している交通系ICカードです。
Suicaにチャージした電子マネーで、鉄道やバスの乗降時に改札へタッチするだけで自動精算できます。また、交通費の支払い以外にも、コンビニエンスストア、自動販売機、飲食店、タクシーなどでの支払いをワンタッチで行うこともできます。
このICカードのキャッチフレーズは「日本を、1枚で」です。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると「Japan in one piece」となってしまいました。
これを直訳すると「日本を一つに」という意味になり、完全な誤訳になってしまいます。
たとえば、「This takes you all over Japan(これで日本全国を巡れます)」や「Travel Japan with one card(一枚のカードで日本を旅しよう)」などの方がよいでしょう。
日本航空株式会社(JAL):明日の空へ、日本の翼
日本を代表する航空会社、日本航空(JAL)のキャッチフレーズは「明日の空へ、日本の翼」です。
これを自動翻訳すると「Japan's wings to the sky of tomorrow」となります。
まどろっこしい言い方になってしまうのと日本を代表する航空会社を知らしめるための「日本の翼」が翻訳すると逆に邪魔になってしまいます。
おそらく「明日の空へ」という部分は、「明るい未来に向かって飛んでいく」という意味として捉えられるので、ここはシンプルに「JAL takes you to the future」でいいのではないでしょうか。
コスモ石油株式会社:ココロも満タンに
ガソリンスタンドの経営をするコスモ石油。
こちらのキャッチフレーズはみなさんもコマーシャルなどでよく聞いたことがある「ココロも満タンに」です。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると「Heart is full too」となってしまいます。
何か、もの足りないですよね。
「ココロも満タンに」の真意はガソリンで車の燃料を満タンにするだけでなく、私たちは同時にあなたの心も満たすサービスを提供します、というものでしょう。
そうであれば「We will fill your car and your heart」の方がよいでしょう。
電源開発株式会社:電気に、本気
電源開発株式会社(J-Power)は電気の供給会社です。
最近では、環境に優しい水素発電技術を開発したり、カーボンニュートラルと発電を両立させたりするような事業を積極的に行っている会社です。
そんな会社のキャッチフレーズは「電気に、本気」です。
電気と真剣に向き合って、時代にあった、もっとも適切な電気を発電したり、供給したりしている、という気持ちが伝わってきます。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると「Serious about electricity」となります。
文法的にも意味合い的にも間違いではありません。
しかし、日本語でせっかく「電気」と「本気」で韻を踏んでいるので、英語でもそのようにしたいと思いませんか?
たとえば、「Facing electricity seriously」とすれば、英語になっても「-city」と「-sly」で韻を踏むことができます。
株式会社ファミリーマート:あなたとコンビにファミリーマート
説明するまでもなく、コンビニエンスストア大手のファミリーマートです。
ファミリーマートのキャッチフレーズは「あなたとコンビにファミリーマート」です。
このキャッチフレーズはテレビやラジオのコマーシャル、ファミリーマートの店舗でもよく流れているので、知らない人は少ないと思います。
このキャッチフレーズを自動翻訳すると「Family Mart for you and your convenience」
となってしまいました。
直訳すると「あなたとあなたの便利のためのファミリーマート」です。
このキャッチフレーズの翻訳で難しいのは、日本語の言葉あそびがキャッチフレーズに含まれている点です。
コンビニエンスストアを意味する「コンビニ」をパートナーを意味する「コンビに」にかけているからです。
自動翻訳した「Family Mart for you and your convenience」には、その面白さが抜け落ちてしまっています。
このような言葉遊びを外国語でそのまま生かすかすのは至難の技ですが、「Combination of Family Mart and You will be your convenience(ファミリーマートとあなたの組み合わせがあなたの便利になります)」の方が、原文に近い気がします。
株式会社西友:安いクセして
食料品、衣料品の小売店を経営する西友。
西友のキャッチフレーズは「安いクセして」です。
しかし、このキャッチフレーズをそのまま自動翻訳してしまうと「He's so cheap」となってしまいました。
「Cheap」は「安いだけ」「ケチな」「質が悪い」というネガティブなイメージを持つ単語です。
日本語の「安いクセして」には「安いクセして、いいもの置いてある」「安いクセして、おいしいものがある」という意味で使われています。
なので、ここは素直にそう言ってしまった方が良いでしょう。
たとえば「It’s so cheap but high quality」や「High quality goods with low price」などです。
誤訳や翻訳の失敗を回避する方法
ここまで挙げた事例からわかるように、ちょっとした翻訳の失敗により、せっかくの新製品が「品質に疑問があるのではないか」と誤解され、販売数が伸び悩むことになったり、ブランドイメージを高めるための翻訳が、逆にブランドイメージを下げてしまったりすることがあります。
翻訳は目に見えにくい部分でありながら、影響は計り知れません。
だからこそ、正確で信頼性のある翻訳が求められるのです。
誤訳や翻訳の失敗を防ぐポイントを以下に示しておきます。
専門分野に強い翻訳会社を選ぶ
翻訳には分野ごとの専門性が不可欠です。
医療、法律、IT、金融など、それぞれの分野に精通した翻訳者を選ぶことで、誤訳リスクを大幅に減らせます。
ネイティブチェックのある翻訳会社を選ぶ
翻訳後に必ず翻訳先の言語のネイティブスピーカーによるチェックを行うことが重要です。
言葉の自然さや文化的背景の適切さを確認することで、より質の高い翻訳が実現します。
クライアントと密なコミュニケーションが取れる翻訳会社を選ぶ
翻訳者や翻訳会社は、クライアントの意図や目的を正しく理解する必要があります。特にキャッチコピーや広告翻訳では、単語の選び方ひとつで印象が大きく変わるため、事前のヒアリングや、その都度都度の打ち合わせが不可欠です。
このような密な打ち合わせに対応してくれる翻訳会社、または気になったことはいつでも気軽に相談ができる翻訳会社を選ぶようにしましょう。
まとめ
翻訳の失敗は単なる「ちょっとしたミス」ではなく、時に大きな損害や人命に関わる深刻な結果を招きます。
ビジネス、医療、法律、行政、ITなど、あらゆる分野で翻訳の重要性がますます高まっている現代において、質の高い翻訳は不可欠です。
本記事で紹介したような失敗事例は、決して他人事ではありません。
翻訳したい文書がある際には、単に言葉を正しく置き換えることではなく、文化と文化、人と人をつなぐ架け橋となることを心がけている弊社にお気軽に相談してください。
株式会社LA ORG
(https://la-org.com/)
- この記事にいいね!する
この記事を書いた人

- 1752いいね!
稼働ステータス
◎現在対応可能
- 桝村 翼
職種
その他
その他
希望時給単価
10,000円~30,000円
株式会社LA ORG 代表取締役の桝村翼と申します。 当社では、英語・中国語・韓国語・フランス語・タイ語・ベトナム語に対応した翻訳・ローカライズ事業を中心に、WordPressによるWebサイト制作、Adobe XD / Photoshop / Illustrator を活用したWebデザイン制作を展開しています。 また、英語学習支援にも力を入れており、小中学生向けの英語学習塾を経営しています。 現在は、世界シェア第4位のグローバル製薬メーカー日本法人様をはじめ、プライム市場上場企業グループ会社様、NASDAQ上場を控えるベンチャー企業様など、業界を問わず多くのクライアントと取引実績があります。 クラウドソーシング(Lancers/CrowdWorks/ココナラ)でも継続的にご依頼をいただいており、SSサロンを通じては翻訳・リサーチ・海外対応等、専門性の高い案件も多くご相談いただいています。 📌 経歴 2015年 神戸市外国語大学 英米学科 卒業 2015年 三井倉庫HD 入社:アメリカ・マレーシアにて物流・フォワーディング業務に従事 2020年 三菱重工業 入社:国産ジェット機「MRJ/スペースジェット」、およびボーイング向けの調達業務を担当 2022年 Schneider Electric 入社:エネルギー分野(UPS)にて海外サプライチェーンを担当 2022年 株式会社LA ORG 創業:翻訳・Web制作・英語教育の3事業を軸に、グローバル支援サービスを提供 🔗 各種リンク 【公式サイト】https://la-org.com 【ポートフォリオ】https://www.portfolio.la-org.com 【Lancers】https://www.lancers.jp/profile/oregonian_office?srsltid=AfmBOop2KwuI5Nr4TQFKMAkwdSj2SAHEAC2A9ZadoikM7A-rmHXQjVdk 【CrowdWorks】https://crowdworks.jp/public/employees/3425349/ 【ココナラ】https://coconala.com/users/2204682?srsltid=AfmBOoqYND8AKR3YqHKQ3-BxWOkyg3sz0PsR36KnLqErFCjzVGkV4nGn
スキル
英語
Adobe Illustrator
WEBサイト設計
・・・(登録スキル数:8)
スキル
英語
Adobe Illustrator
WEBサイト設計
・・・(登録スキル数:8)